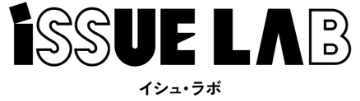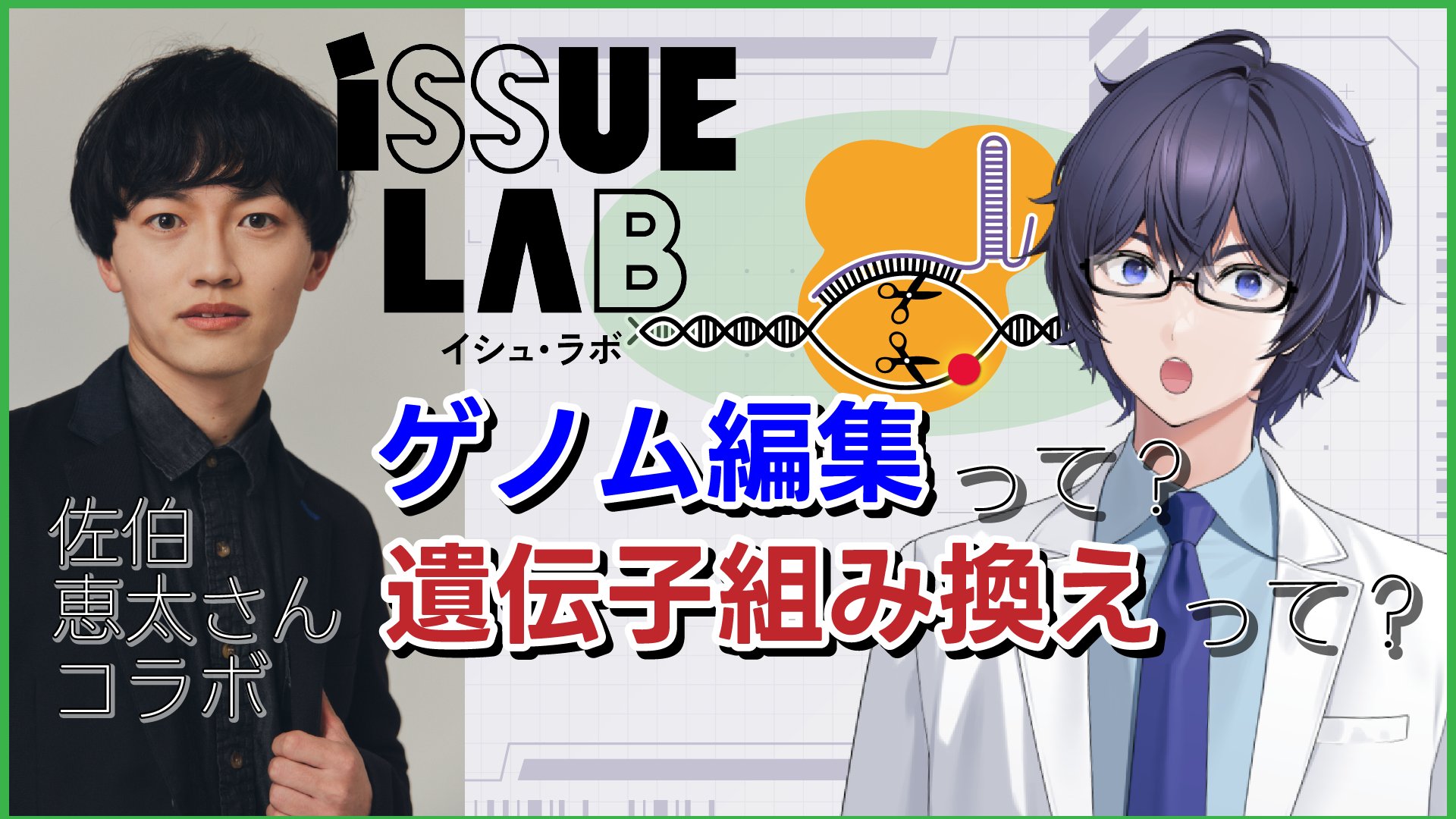【高遠頼】学術系VTuberに聞く!身近で誠実なサイエンスコミュニケーションとは?

高遠頼(生命科学系VTuber)/ 聞き手・文:佐伯恵太(サイエンスコミュニケーター)
学術系VTuberとして活躍されている高遠頼さんに、俳優・サイエンスコミュニケーターとして活動する佐伯恵太さんが、お話しを伺いました。
学術系VTuberとは、バーチャルYouTuberのうち、特定ジャンルの専門家として活動するVTuberの総称です。「言語学」「水産・海洋」「服飾」「法律」「天文学」など、さまざまな分野の発信を担う学術系VTuberが存在しますが、高遠さんは、生命科学系VTuberとして活躍されています。
科学を発信したり、科学と社会の問題について議論する上で、押さえるべきポイントについて、高遠さんと佐伯さんが意見を交わしました。
生命科学系VTuber誕生のきっかけ

佐伯:高遠さんが活動を始めたきっかけを教えてください
高遠:私が、本格的に活動を始めたのは、COVID-19がちょうど流行り始めた2020年3月ごろです。その前からニコニコ動画などで(VTuberとしての姿ではなく)ゆるく発信活動はしていたのですが、コロナ禍で、まさに未知のウイルスということで、誤った情報が出回ったりしているのを目の当たりにして、何かできることがあればという気持ちで始めたのがVTuber としての活動のきっかけです。
当時は、学術系VTuberという言葉も浸透していない黎明期でした。本格的に発信をしていくにあたり、なるべく親しみやすいかたちで観てもらえたらという想いもあり、VTuber というかたちでの活動を始めました。
佐伯:発信されていたのはどんな内容だったのでしょうか?
【佐伯恵太さんにサイエンスコミュニケーションについて聞いた記事も併せてどうぞ】

高遠:まさにコロナ禍ということで、新型コロナウイルス自体の説明や、「PCRとは?」「ソーシャルディスタンスとは?」といった新型コロナ関連の動画を公開しました。さらに、再生医療や合成生物学の話など、幅広く生命科学に関する発信を行っていました。
生物学の分野は多岐にわたりますし、それぞれが重要かつ魅力的な分野です。一方で、様々な情報が錯綜し、新型コロナ関連の情報と同じく、誤った情報も多く見られます。そこで、生命科学の正確な情報を届け、議論し合い、ともに高め合っていきたいと考えました。
佐伯:情報を伝えるだけでなく、双方向でのやり取りも意識されているのですね
高遠:YouTubeに投稿した動画には様々なコメントをいただけるので双方向のプラットフォームと言えると思いますが、より双方向性の高いライブ配信も行っています。ライブ配信では、リアルタイムでコメントをいただき、即座に話す内容を変えていけるのが特徴です。1時間以上の配信でも最後まで観ていただけることも少なくありません。
佐伯:配信の内容はもちろん「場を楽しむ」という要素が大きいのかもしれませんね
高遠:そうですね。配信は皆さんと一緒に作っているという感覚が強いです。また、視聴者さんの中には、生命科学の専門家ではなくても、別の分野の専門家の方も多く、別の分野の視点でのコメントなど、私も勉強になることが多いです。
佐伯:議論し合い、ともに高め合う場が実現していますね!
「わからない」ことの怖さを超えて楽しむこと

佐伯:今までたくさんの活動をされてきた中で、何を大切にされていますか?
高遠:「科学の面白さ」を伝えるということが一つにはありますが、「自然の怖さ」というところも同時に伝えたいなと。ウイルスなんかも含めて、生物や自然現象にはまだまだよくわかっていないこともあります。
「わからない」ことに対する怖さというのは当然ありますよね。一方で、「わからない」ことを楽しむ姿勢というか、そういう雰囲気を皆さんと一緒に育んでいけたらなと思っています。
佐伯:社会においては「わからない」ということが実害に繋がるケースもありますが、「わからない」ことこそが研究の出発点であり、醍醐味でもありますもんね
高遠:ウイルスのなかでも、エボラとか狂犬病とかなら発症すると致命的になるので、その危険性というのを知ってほしいです。一方で、感染した場合の致死率が極めて高いようなウイルスばかりではなく、過剰に恐れる必要のないものもある。そうした「正しく恐れる」感覚や、そのための知識を誠実に伝えていけたらと思っています。
また、新しい技術を身近に感じていただくことも大事ということで、レプリコンワクチンが市場に出て間もなく、実際に打ってきて、それについて解説するという配信も行いました。
まず、レプリコンワクチンについて伝えるために、そもそも、mRNAワクチンが、これまでの生ワクチン、不活化ワクチンとどう違うのか、レプリコンワクチンのmRNAを自己複製する仕組みはどうか、順を追って、客観的に説明しました。話題となった「接種者からウイルスが感染する」説の「シェディング」についても触れて、接種者からの感染結果が論文などで報告された事実はないことを伝えました。
ただし、言っておきたいのは、この配信は、自分が打ったから推奨するという意図ではなかったということです。
私自身は、新しい技術を応援するという意味も込めて打ちましたが、既存のワクチンと比較して、なるべく客観的に伝えた上で、皆さんに選択していただければと思って配信を行いました。
佐伯:Xでも多数発信されていますが、心がけていることはありますか?
高遠:Xでは何気ない日常に関するポストもありますが、論文解説も行なっています。最近では、宇宙ステーション(ISS)での味噌作りに関する論文を取り上げて大きな反響がありました。論文が公開されてから、早いもので翌日、基本的には1週間以内には取り上げるようにしています。
佐伯:「正確な情報を早く出してバズる」ことは、最初に誤情報に触れてそのまま信じてしまう人を減らすという意味でも、大きな意義があるように思います
社会課題をサイエンス × エンタメ!
佐伯:この度、高遠さんに「イシュ・ラボ」メンバーとして加入いただいたということで、「イシュ・ラボ」のテーマや活動と絡めて質問していきたいと思います。

社会課題となっているテーマや伝わりにくい科学技術をサイエンス × エンタメで、楽しく・わかりやすく伝えるプロジェクト。現在、第一弾企画として、遺伝子組み換え作物に関する解説動画やショートドラマなど、複数のコンテンツを公開中。
佐伯:高遠さんが科学について発信する時、「科学と社会の関わり」の観点から意識していることはありますか?
高遠: 先ほどの_レプリコンワクチンの例だと、ワクチンに関する基本的な情報をお伝えするとともに、科学的な観点だけでなく、多面的に捉えて発信するようにしました。
しかし、最終的には、一人一人の生活の中での意思決定だと思うので、そういうところは意識していると思います。
また、最近の配信ではマンモス復活プロジェクトについて取り上げました。マンモス復活を目指すColossal Biosciencesというベンチャー企業が、モフモフの毛を持つマウスを誕生させたという内容です。
実際、毛の長いマウスとマンモス復活は、サイエンティフィックには距離がだいぶ離れている話です。そもそもこのプロジェクトは、ベンチャー企業による研究で、出資を募るために、キャッチーな話題が必要という背景がありました。このように、研究そのものの中身だけでなく、プロジェクトの背景など全体像を押さえて発信するように心がけています。
ゲノム編集技術で実際に狙い通りにモフモフのマウスが実現できた部分はスゴいなと思いつつも、科学的に見てどれほどの新規性があるのか、実際にマンモスが復活できたとして今の環境で生きていけるのかなど、生命倫理的な観点も含めて議論しなくてはいけないと思っています。
佐伯:ゲノム編集のお話も出ましたが、イシュ・ラボでは遺伝子組み換え作物を題材にしたコンテンツを公開しています。遺伝子組み換え作物自体や、それに対する社会の認識について何か思うことはありますか?
高遠:研究者・事業者・消費者それぞれの目線で考えたいですね。研究者としては技術的にどういうことが可能なのかというところ、事業者としては実用性、収益も極めて重要かと思います。消費者目線でいうとやはり安全性ですね。
最近では遺伝子組み換え作物に加えて、より精度の高いゲノム編集技術で作られた作物もありますが、それでも完全にターゲット遺伝子だけを編集できるわけではありません。オフターゲット効果と言って、編集しようとした遺伝子以外の場所を誤って切断してしまったり変異を起こしてしまう現象があります。
それによって必ずしも人間に悪い影響を与えるわけではありませんが、消費者からすると、悪い影響があるかもしれないという点には敏感になるでしょうし、不安感はあると思います。
佐伯:予想外のところで遺伝子の配列が変わってしまうという意味では、従来的な育種(品種改良)も、何かが改良されている以上は遺伝子配列が変わっているはずですが、そこに不安を抱く人は少ないですよね
高遠:確かにそうですね。どうして育種は受け入れられて、遺伝子組み換えやゲノム編集が受け入れられにくいのかという問題は、ぜひ考えた方が良いですね。今私たちが食べている野菜は、元々の野生種とは形や性質が大きく異なるものも多いわけです。長い歴史を重ねて現在の野菜の姿になっているということについて、人々は、どう感じているんでしょうね。

佐伯:遺伝子の配列が変わる度にその影響度を検証するなんてことは行われていませんし、そもそも人類の歴史の中で、生物の遺伝子情報が読み取れるようになったのはごく最近の話ですしね。「わかる」とそのリスクが気になってくるのか・・・
高遠:そのあたりは興味深いですね。配信で視聴者さんに聞いてみるのも良いかもしれません。
佐伯:それは良いアイデアです!ぜひお願いします!
高遠:わかりました!遺伝子組み換え作物に限らず、遺伝子組み換え技術に関する最新のトピックや、イシュ・ラボでの私の構想なども含めて配信でお話できればと思います。
佐伯:思いがけずスペシャルなライブ配信まで決まってしまいましたが、高遠さんと今後も色々なかたちで、イシュ・ラボで活動していける可能性を感じました!ありがとうございました!
高遠:ありがとうございました!リアル、バーチャルの垣根も超えて、みんなで盛り上げていけたら良いですね!
【高遠頼さんYouTubeチャンネル】
高遠_頼 生命科学Channel
生命科学を初めとする、科学全般についての動画を投稿。科学についての知識が少ない方でも、科学について詳しく知っている方でも、面白く楽しめる動画となっている。
【プロフィール】

高遠頼(生命科学系VTuber)
YouTube や X にて活動している生命科学系VTuber。専門は合成生物学、バイオインフォマティクス、データサイエンス。
Ph.D. 博士(理学) 学振DC1、バイオインフォマティクス系IT企業を経て、化学メーカーにて生命科学の研究者として従事。

佐伯恵太(俳優・サイエンスコミュニケーター)
1987年、京都府生まれ。京都大学大学院理学研究科で修士号(理学)を取得し、日本学術振興会特別研究員(DC1)として同大学院博士後期課程に進学。1年間の研究活動の後、俳優に転身。現在は、科学とエンターテイメントの架け橋になるべく、フリーランスの俳優・サイエンスコミュニケーター(科学コミュニケーター)として活動中。
[個人サイト]
https://keitasaiki.info/