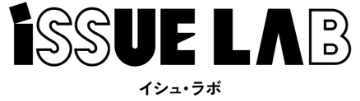【佐伯恵太】サイエンスコミュニケーションとエンタメの力で、ひとの心に寄り添う

佐伯恵太(俳優・サイエンスコミュニケーター)
サイエンスコミュニケーターとして活躍する佐伯恵太さんの科学への興味は、幼少期の昆虫採集から始まりました。その原体験から、学生時代は生物学の道に進み、生物の進化の仕組みを解き明かすことにロマンを感じていたといいます。
同時にエンターテインメントへの興味もあった佐伯さんは、俳優の道に進んだ後、科学とエンターテインメントを横断する領域で、サイエンスコミュニケーターとして活動を始めます。
「科学をみんなのものにする」ことがサイエンスコミュニケーターの役割だと語る佐伯さん。一方的に科学を伝えるのではなく、役者として培った経験で、相手の興味や感じ方をリアルに考えて寄り添うことを大切にしているとのこと。不安な意識を持つ方も多い技術である「遺伝子組み換え」に関するコミュニケーションのあり方について、佐伯さんに話を聞きました。
採れる昆虫は何でも採っていた幼少期

──佐伯さんはサイエンスコミュニケーターとして活躍されていますが、そもそも科学に興味を持ったのはいつ頃からなのですか?
佐伯:物心がついた頃からですね。生まれは京都市内で、田舎というわけではなかったのですが、自然豊かな京都御苑や、たまに山の方に行って虫採りをしていました。あと、親に連れられて京都市青少年科学センターにもよく行っていました。
母に聞くと「2歳から虫を追っかけていた」と言います。昆虫採集と昆虫図鑑を眺めるのが好きな幼少期を過ごしました。カブトムシとかクワガタムシとか、いわゆる甲虫が特に好きでした。他にもバッタやセミ、アリやトンボ・・・。採れる昆虫は何でも採っていましたし、飼育もしていました。
──飼育もしていたんですね。
佐伯:「アリジゴク」として知られるウスバカゲロウの幼虫を神社の境内から採って来て、瓶に砂を入れて飼っていました。ラジオ体操に行ったら小さなアリを1匹捕まえて帰り、アリジゴクにやったりして。途中で放棄せず、ちゃんと成虫になって、飛ぶところまで見届けました。
アリジゴクはアリが落ちて来るのをただ、待ち構えているのではなく、近寄って来るアリの頭上に砂を放り投げ、その砂が土砂崩れのようになることで落ちて来るアリを捕食するんです。そんなアリジゴクの戦略を知って子どもながらも「凄い!」と驚き、感動しました。
──そうした体験がきっかけで昆虫の研究を始めることになったのですか。
佐伯:原体験が昆虫だったので、生物学が最も楽しく勉強できました。それで京都工芸繊維大学に進学し、蚕の研究をしていました。
京都工芸繊維大学は、母体が京都蚕業講習所だったということもあり、蚕の研究が盛んだったんです。蚕は繭を作る時、絹の糸を吐きますが、体全体を覆い尽くす糸を作るため、絹糸腺という器官で大量のタンパク質を合成します。これは凄い能力です。この能力を応用して無細胞タンパク質合成系と言われる、カイコ由来のタンパク質合成工場を作るような研究に取り組んでいました。
研究は、どのような条件ならより沢山のタンパク質を作ってくれるかを調べるというもの。反応液の色々な物質の量を調整したりしながら、最適な条件を求めるべく実験結果をひたすら記録しました。
研究として意義があることは理解できても、私のモチベーションである“生物に対する心躍る感動”とはギャップがあって。『生きている昆虫の生態や行動を研究したい。もっと俯瞰して進化にせまるような研究もしてみたい』と思い、京都大学大学院の研究室に進みました。
生物の進化を解き明かす研究に、壮大なロマンを感じる

──京都大学ではどのような研究をされていたのですか?
佐伯:「暗黒バエ」の研究です。これは、長期の暗闇環境が生物に与える影響を調べるというもので、1954年に京都大学理学部動物学教室の森主一教授によって開始されました。
当初は「暗い深海や洞窟にいる生物は眼が退化している。人工的に暗闇にすることで眼は退化するかもしれない」といった仮説のもと、進化を見るという研究でした。私の時代は、ゲノム解析を取り入れるなど、様々な研究が行われていました。
対象の生物はショウジョウバエ、遺伝学や分子生物学の実験でよく使われる、研究用途に適したモデル生物です。自分が実験していた当時で57年間も暗黒で飼育を続けていました。約1400世代、人間でいうとクロマニョン人から現代人までといったスケール感です。
蚕の研究では気づきもありましたし、生物学を学ぶことが楽しかったです。ただ、もっと生物学を突き詰めたいと思い、京都大学なら暗黒バエという興味深い対象を、行動レベルで研究できる。そして、昆虫採集をしているだけでは分からない、生物の進化の不思議や仕組みを解き明かせられる、そんなことに壮大なロマンを感じました。
研究者から俳優。そしてサイエンスコミュニケーターへ

──佐伯さんは、その後、俳優に転身されています。
佐伯:5歳から水泳を習い、高校では競泳選手でした。その頃、映画やドラマで『ウォーターボーイズ』が流行っていました。男子高校生がエンタメチックなシンクロナイズドスイミング(現:アーティスティックスイミング)を文化祭で披露するために挑戦するというストーリーです。
それを見たことがきっかけでシンクロナイズドスイミングを真似事で始めました。もともと、エンターテインメントへの想いがあったとか、芸能界に行きたかったというわけではないですが、高校3年の時、テレビ番組の『全国高校ウォーターボーイズ選手権2』に出演したことで、エンターテインメントや芸能界に興味が芽生えました。
その後、選手権で出会った全国の仲間を中心に有志のチームが結成され、大学時代もそこに参加し、夏休みの半分はアルバイトをしてお金を貯めて、残りの半分で合宿をしてショーに出るということをしていました。
──研究とパフォーマーを両立されていたのですね。
佐伯:夕方まで研究をしたらラボを出て、皆が集まっているプールに行って徹夜で練習をして、朝、またラボに行って研究をするという生活をしていました。
──こうした体験が、後々の、サイエンスコミュニケーターにつながって行くわけですね。
佐伯:人に教えることも好きだったので、大学の頃に有志のチームを作ってサイエンスコミュニケーターのようなこともやっていました。
例えば、子ども向けに、科学に関するワークブックを作り、それを使ったワークショップを開催するとか。ワークブックに子ども達が思ったことを自由に書き込んだりシールを貼ったり絵を描いたりすることでそのワークブックが完成するみたいな。そんなオリジナルコンテンツを作って活動をしていました。
その頃、『これを仕事に出来ないかな』という考えもよぎったのですが、当時はまだ、サイエンスコミュニケーターというもの自体が今より普及していませんでしたし、自分自身の経験値やスキルも不足していました。それで、エンターテインメント、芸能の道を選択しました。
そこから経験も積んできたことで『今ならできる!』と思い、エンターテインメントと科学を横断する領域でサイエンスコミュニケーターとして活動することにしました。シンクロチームの解散後は、俳優として現在まで活動していますが、そこでの経験が大いに役に立っていると感じます。
「科学をみんなのものにする」 ための役割を果たす

──サイエンスコミュニケーターの役割は何だとお考えですか?
佐伯:サイエンスコミュニケーターを日本語にすると「科学に関する意思疎通をする人」となると思いますがよく分かりません(笑)。「科学と社会をつなぐ」ことが役割ですが、私は「科学をみんなのものにする」くらいの、大枠なものとして捉えています。
研究者や科学技術を駆使している企業・技術者といった、一部の人達だけが最新の科学技術や研究成果を享受できるのではなく、もっと広く、科学や研究を教養や娯楽として楽しむ人にも提供する。
実際、科学ファンは沢山います。あるいは最新の科学や研究を学ぶことでビジネスに活かす。はたまた、自然災害やパンデミックなどの有事の際に科学的な見方、考え方に基づいて「自分はどうすればいいのかを判断したい」という方もいます。もちろん、科学を知りたい、活用したいと思っている人以外でも、実際に科学に触れたり学ぶことで、楽しめたり活かせることは大いにあります。
そういう、全ての人に対して「科学をみんなのものにする」ことが、サイエンスコミュニケーターの中心的な役割のひとつだと考えています。もちろん、それはサイエンスコミュニケーターに限らず、研究を発信する研究者や理科教師、科学・理系に強いジャーナリストなど、科学に関わっている人達全員が達成して行くことだと考えています。
──佐伯さんはどのように活動されているのですか?
佐伯:例えば脳科学の市民公開講座のファシリテーターを務めることもありますし、音をテーマに子ども向けのサイエンスショーを、とオーダーされ、実演することもあります。
フリーランスという前提があるので、基本的には自分の意思決定でどのようなこともできます。そのため、科学にまつわるテーマで、ライターや動画クリエイター、ディレクター、イベントプランナー、司会者、パフォーマー、ファシリテーターなど、様々な活動を行っています。
もちろん、同じような仕事をされている方は多いのですが、自分の強みは「サイエンス×エンタメ」だと思います。例えば、パフォーマーとして振舞う時は表現や伝え方にエンタメ要素を添える。自分が出ないとしても演出的な部分でエンタメのエッセンスを加えています。
社会の声に寄り添うサイエンスコミュニケーターでいたい

──サイエンスコミュニケーターとして、どのようにコミュニケーションをしているのですか?
佐伯: サイエンスコミュニケーションにおいて長年議論されてきた「欠如モデル」というものがあります。これは、「大衆が科学技術を信用しないのは、大衆に情報が欠如しているからだ」。もしくは「大衆の理解が足りないからだ」とする理論です。
しかし、それに対して「一方的に知識を伝えるだけでいいのか」「大衆の素朴な疑問とか、大衆が持つ専門性や現場感は聞かなくてもいいのか」「一方向に知識を伝えるだけで、本当に大衆は科学的な知識を身に付け、科学に対する不信感を払しょくできるのか」という議論が起き、数々の論文を通して欠如モデルの問題点が指摘されてきました。
これは私自身も注意していることです。ただ単に「科学的にはこうです」と伝えるのではなく、社会の声に寄り添うべきです。例えば、新型コロナウイルス感染症では、ワクチンを打つ、打たないという論争やマスクの効果に対してさまざまな声が挙がりました。人それぞれ不安感の強さや置かれた立場も違いますし、様々な要因を踏まえて発言しなければなりません。
いっぽうで、科学的なエビデンスを揺るがせてしまうのは誠実ではありません、「科学的エビデンス」と「伝える対象の意識への配慮」、両方のバランスを取ることが重要だと考えています。
──コミュニケーションの要素としてエンタメがあると思うのですが、どのように取り入れているのですか?
佐伯:よく、「見て楽しめる実験ショーをするんでしょう」と言われます。それはその通りですが、エンタメには楽しさの要素だけでなく、シリアスなものもあります。心に響くような、心を動かすものがエンターテインメントだと考えています。
楽しくて分かり易い実験ショーだけでなく、危機感や緊迫感、社会の切実な想いも、エンタメを活用することで心に響く情報発信ができると考えています。
また、自分のベースは役者です。役者は台本を読み込み、役作りをします。その役作りを踏まえて登場人物になります。それをコミュニケーションでも活かせるのではないかと考えています。問題を他人事にしてしまうと「なぜ、そんなに不安に感じるのか?」と理解不能に陥ります。役作りのときのように、相手の立場や意識を想像してみる。
例えば、「子どもの未来が不安だ」と言われたとき、「私には子どもはいないから理解できない」と思うのではなく、子どもがいたとして考えることで、相手の不安が想像できるようになると思います。
サイエンスコミュニケーションは、相手の意識や立場をリアルに考えることが大事です。「視点を相手に映し、相手になって生きたらどう思うか」ということが重要だと気付き、私は役者として、「相手になって生きる」能力は培ってきたはずなので、それを使って行こうと考えています。
「不安なひと」の味方になるサイエンスコミュニケーション

──遺伝子組み換えに対してはどのようにお考えですか?
佐伯:京都大学大学院時代に実験で用いていたショウジョウバエは、遺伝子組み換え技術が確立している生物です。そんなショウジョウバエで研究してきた身とすれば、遺伝子組み換えは、「技術の実態」と「社会でのイメージ」にギャップがあると感じています。
遺伝子組み換えは、多くの人が安全性を不安視している技術だと思います。もちろん、安全性は大事です。どうやって安全に食を届けるのかは重要です。いっぽうで「メリット」と「デメリット」と「安全性」をバランスよく評価することが大切だと思います。
遺伝子組み換えについて、正しい情報を知ることで、「海外では大々的に活用されているとは知らなかった。」「日本ではまだ栽培されていないのに、積極的に栽培を進めていると勘違いしていた」といったように、少し意識が変わる可能性もあります。
──遺伝子組み換えについて、あるべきコミュニケーションについてどう考えられますか?
佐伯:データ*を見ると、日本では世代間で意識の違いがあることが分かります。遺伝子組み換えについて「怖い・悪いイメージ」を持つひとの割合が、高年齢層には、高く、若年層では、必ずしも高くないという傾向があります。その違いを生んでいる要因のひとつとして、世代ごとの経験や科学に対する捉え方の違いがあると思います。
*出典:バイテク情報普及会(2021年)遺伝子組み換え/ゲノム編集食品に対する消費者の意識調査(20~50代の男女 合計2,000人)https://cbijapan.com/document/4453/
例えば、高度成長期、工業の発展によって日本は経済大国になりましたが、その反面、公害問題も引き起こしました。それを経験している世代は、科学に対して不信感を募らせるのは想像できます。
ただし、高年齢層とか若年層とステレオタイプに捉えて「こうだ」と決めつけるのは危険なことです。若い世代であっても「極めて危険だ」と認識している人もいるはずです。
ひとり一人の気持ちを想像した上で「こういう人がいるかもしれない、ああいう人もいるかもしれない」と考え、遺伝子組み換え作物に関して、「この人はこういう経験をしてきたから、科学的と言われることに危機感を感じるのだろう」と意識を理解してアプローチすることが大事だと思います。
遺伝子組み換えの「不安」に寄り添い、知ってもらう。

──具体的にはどのようにすれば良いのでしようか?
佐伯:これは長崎県長崎市で「農家BAR NaYa」を経営されている渕上桂樹さんから聞いた話なのですが、お店には「農薬はものすごい毒だと聞いたんですが」と質問するようなお客さんが来るそうです。そのお客さんが研究者や科学的なマインドを持った方なら「科学的に安全性はここまで認められています」という話ができます。
いっぽう、その方が専門家でないなら「なるほど。危険だという話を聞かれたんですね」と一旦相手の気持ちを受け止める。そのうえで「実は私の知り合いに農薬を作っている人がいるんです。」「私も知らなかったんですが、思ったよりも安全性を考えていて、農薬について熱く語ってくれたんですよ」という話をするんだそうです。
そうすると「農薬は毒じゃない」と考えを変えるのではなく、自分の聞いてきた「農薬が毒」という話自体は否定しないが、「農薬が安全」という話も同時に聞いてくれて、どちらも共存した状態で受け入れるようになるということでした。
相手が「こういう話を聞いて不安に思っている」という情報を出してくれているにもかかわらず、それを無視して「農薬の安全性の基準値は定まっています」と言っても仕方ありません。
農薬の安全性を基準値で判断しないひともいます。「相手の判断基準はどこにあるのだろう」という想像から入ると、また違ったコミュニケーションが生まれると思います。
──なるほど。これはサイエンスコミュニケーションの大事なポイントですね。
佐伯: 様々な条件や世代、地域、いろんなことを全体的に見て、どう捉えるのか、何の妥当性が高いかを考える必要があります。
ただし、サイエンスコミュニケーターが自分の中のサイエンスベースの基準をずらしてしまうのは問題です。それでは、サイエンスコミュニケーター自身が“リスクの拡声器”になってしまいます。「不安な気持ちのひと」の味方であるはずが、不安をあおるような立場になることは避けるべきです。
──今後、「遺伝子組み換え」についてのコミュニケーションに取り組まれるとか?
佐伯:現在、遺伝子組み換え作物をテーマにしたショート動画制作に、企画や出演など様々な形で携わらせて頂いています。
YouTubeにショート動画として投稿できる動画は60秒以内、TikTok等でも短い動画が好まれる傾向にあるので、ある程度削ぎ落してシンプルにメッセージを伝えるのが効果的だと考えています。
「科学的な安全性評価」と「社会の不安感」にギャップのあるテーマなので、少しでも「遺伝子組み換え作物に対して不安だったけど、知らないことが知れて良かった」と思ってもらえると良いと考えています。クイズや解説動画の他、ショートドラマにも挑戦しました。こちらの動画では脚本、出演などを担当しているのですが、短い物語を通して、科学や研究者を身近な存在に感じていただけたらと、想いを込めて作りました。
今後、遺伝子組み換え作物に関係する様々な立場の方と連携して、まだ知らない人に情報を届けたり、「不安を感じるひと」に寄り添ったサイエンスコミュニケーションができればと考えています。
【プロフィール】
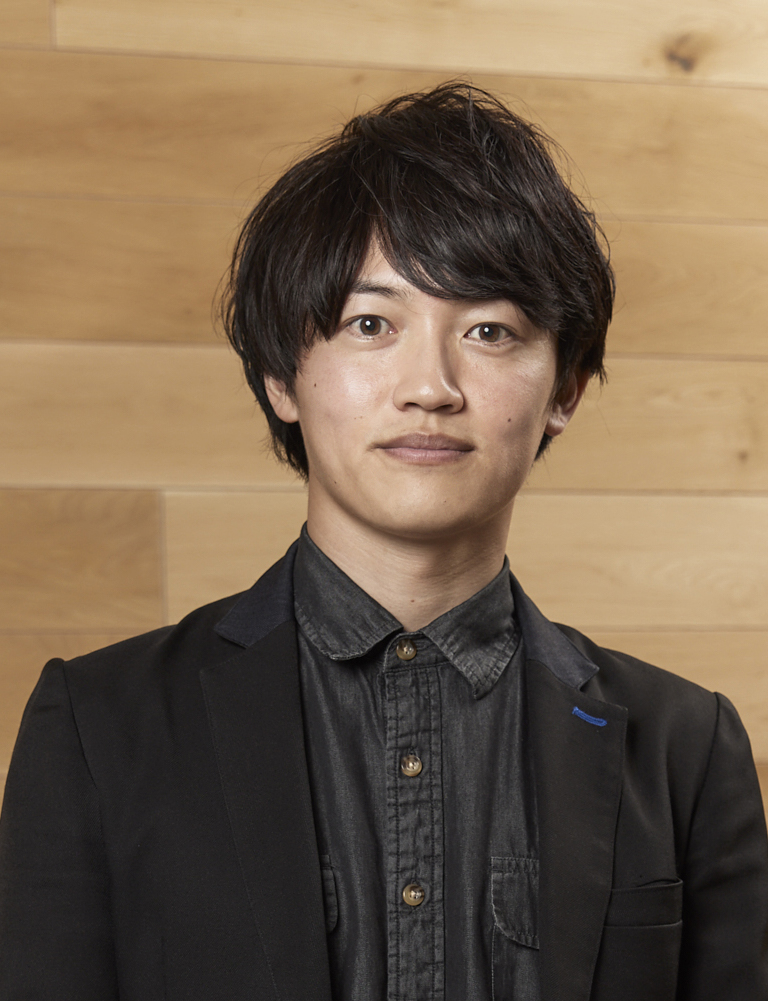
佐伯恵太(俳優・サイエンスコミュニケーター)
1987年、京都府生まれ。京都大学大学院理学研究科で修士号(理学)を取得し、日本学術振興会特別研究員(DC1)として同大学院博士後期課程に進学。1年間の研究活動の後、俳優に転身。現在は、科学とエンターテイメントの架け橋になるべく、フリーランスの俳優・サイエンスコミュニケーター(科学コミュニケーター)として活動中。
[個人サイト]
https://keitasaiki.info/
Sponsored by バイテク情報普及会